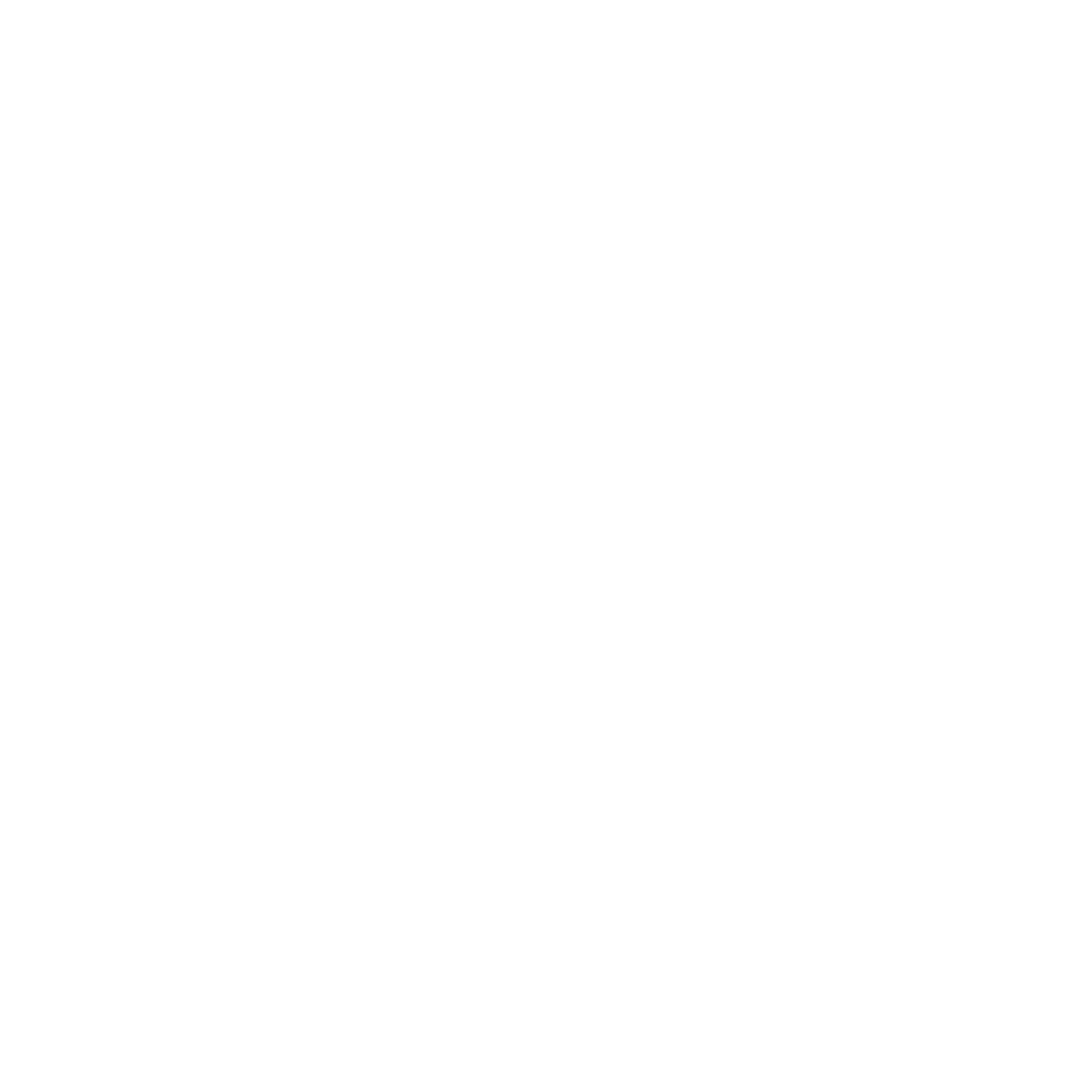コメント
『堕ちる』村山和也監督待望の新作にして初の長編映画、ということ以外、予備知識を何も入れずに観始めたのだが、序盤、それこそ「とら男」役の西村虎男さんが喋りだしたあたりから生じたある恐ろしい予感は、その後どんどん、確信へと変わっていった……「ひょっとしてこれって、ホントの話?」「そしてこれ、ホントに“本人”じゃない?!」「って、なんて映画の作り方するんだ!?」。地を這うようにドキュメンタリックな日本地方都市ノワール、という前作から引き続きのテイストを、方法論として革新的なレベルまで一気に飛躍させた、これはまさに一世一代の驚異的劇場デビュー作! クライマックスで「とら男」が見せる視線は、『ゾディアック』をも突き抜ける。
ライムスター宇多丸(ラッパー/ラジオパーソナリティ)
とにかく実在の元刑事“とら男”さんのキャラクター、芝居、いや芝居と言っていいのかさえも分からないリアリティ、それらがとにかくすごい。そして事件にかかわる証言者たちの佇まい、あり方、その場に自分たちが立っていると勘違いするほど迫ってくる。ドキュメントとフィクションの垣根を超えたとか言ってる場合でなく、これは紛れもなく映画として屹立しており、何にもまして、友情と成長と諦念のドラマがシンプルに芯を貫き通しているからこそ出来た離れ業。脱帽!
瀬々敬久(映画監督)
この映画の凄さは主人公のもと刑事・西村虎男の目力だろう。未解決の水泳コーチ殺人事件を退職後も調べる主人公を、当時本当に事件を担当した刑事本人が映じているのだから、そのリアリティと迫力は半端ではない。リアル『殺人の追憶』といってもいい映画だ。
柏原寛司(脚本家・映画監督)
事件を実際に捜査していたホンモノの刑事がそのまま出演するという驚天動地の設定に思いきり惹かれた。そして主演「とら男」さんの眼力と演技力はハンパなく、圧倒されました。鬼刑事、すごい。
佐々木俊尚(作家・ジャーナリスト)
どこまでが本当なの?と聞きたくなるこの映画は、フィクションでもなくノンフィクションでもなく。リアルと想像を物語に仕上げる。とら男の終盤に見せた目つき。怖い。これは、新たなエンターテイメントの形であると思う。すごい。考察が尽きない映画だ。
鈴木おさむ(放送作家)
チラシの迫力に、オオカミ男のような話かと一瞬思わせますが、実在の主人公の名前でした。そして、実際に起きた事件のドキュメンタリー的な要素と劇映画の融合は、すこぶるリアルなイリュージョンを生み出します。これ以上の説明は不要、珍品なので、とにかく観ないと損をします。
松尾貴史 (俳優)
実在の事件を担当した元刑事が本人を演じて、フィクションだからこそ描ける真実に挑戦。大胆にも、バディムービーとして展開する作りに、モデルのない映画へと突っ走る心意気が伝わりました。全てに真摯に応える、とら男さんの魅力に釘付けでした。
前田弘二(映画監督『まともじゃないのは君も一緒』)
フィクションがノンフィクションの側へ越境するのか、それとも、ノンフィクションがフィクションの側へと越境してくるのか。どちらにせよ、“実際の未解決事件”というモチーフに対するナラティブな制約、或いは、表現の制約といった壁を、『とら男』は悠々と飛び越えてゆく。フィクションとノンフィクションとの境界を、まるで“水面”のように千変万化させているのだ。重要なのは、「本当にあったのかどうか?」という真実の在り処ではない。ある事象が、時代の風雪に耐えきれぬまま世の中から忘却されたとしても、いち個人が「忘れない」ことに意味があるのだと考察させている点にある。さらに、いつの間にか観客の脳裏へ“実際の未解決事件”の記憶が刻まれているという、巧妙な罠まで仕掛けられている。そのプロセスを提示することで、「覚えている」ことと「忘れない」こととが似ているように見えて、実は全く異なるメカニズムであることを、この映画は可視化させているのだ。こんなアイディアを思いつき、製作に動いたなんて、すごい才能だと思う。
松崎健夫(映画評論家)
村山和也監督が初の長編を撮ると耳にしたのは、2019年の後半だったか。題材は、ホントにあった殺人事件。迷宮入りとなったその事件の再捜査に挑む元刑事役には、かつて捜査に携わっていた本人、しかも演技経験などない方が就くと、クランクイン前の高揚と不安が伝わってくる、監督本人から聞いた。一体どんな映画になるのか?皆目見当がつかなかった。やっとの思いで手掛ける初長編に、なぜこの題材を?正直言って、困惑もした。それから3年近くが経ち、完成した作品を観て、舌を巻いた。考えてみれば彼の前作、中年の職人が地下アイドルに入れあげて、破滅の道を辿る短編『堕ちる』でも、実際のアイドルが、ほぼ本人を演じていた。現実と虚構、その間に漂うものにリアリティーを持たせる。実に危うい手法にも思えるが、それを掴み取って描出できれば、正に「映画的」なものとなるのかも知れない。元刑事を“再捜査=映画の世界”に誘い、スクリーンに対峙する観客のガイドをも務める女子大生役に、加藤才紀子という、“普通”を装える頼もしい才能を得て、村山監督は確かにそれを、やってのけたのだ。そして『とら男』はいま、世に放たれる。
松崎まこと(映画活動家/放送作家)
物事に終わりは付き物。しかし、その終わりに納得できなかった時、何をもって“終わり”としたら良いのだろう。終わりなくして始まりなし。心の折り合いもつけられず、過去に囚われたまま生きてきいくのは辛いこと。元刑事と大学生の出会いによって、止まっていた時計の針が少しずつ動き出す。どう納得するのか、どう折り合いをつけるのか、どう終わらせるのか。自分自身にも思い当たることがあり、とら男の姿から目が離せなかった。あの鋭い眼光が心に焼き付いた。
ミヤザキタケル (映画アドバイザー)
殺人事件絡みのミステリー調なのに、ほのぼのムードの異色バディムービー。劇中に混ざるドキュメンタルな感触。ココロに残るのは、とら男さん&かや子さんの「再生と成長」。色んな具の入ったおでんのような、超ジャンル的でユニークな組成の映画。どうやったらこんな味が出せるんだろう!?
森直人(映画評論家)
未解決事件の映画化に当たり、実際に捜査にあたった刑事本人が主演するというだけでも驚愕だが、現実とフィクションがメビウスの輪のごとく繋がる展開に惹き込まれずにいられない。真実は、フィクションの中にあるのか、それとも…。鑑賞者は証人だ。こんな映画、見たことない。
矢田部吉彦(前東京国際映画祭ディレクター)
虚を通して実に迫る。それを支えるのはとら男の圧倒的な存在感。あの視線を真正面から記録したことが本作の武器だ。世界レベルで勝負が出来る傑作だと思う。
松江哲明(映画監督)
同調圧力や忖度により真実が歪められ、たちまち風化してしまう今の世の中で、口をつぐみ思考を止めるべきではないとあらためて思う。この事件の背景やその後も気になるし、村山監督の今後にも期待したい。
下田法晴(ミュージシャン/SILENT POETS)
ポジティブという言葉が持て囃され、 誰もがそれを標準装備して然るべきとされる時代に なってから十年は過ぎた。 その既定路線からこぼれ落ちる人たちの姿を やさしく掬い上げ、それぞれのやり方で控えめに、 しかし確実に歩を前に進めていく様子を 描くことで、村山監督は観る者に希望を与える。
ジェーン・スー(コラムニスト/ラジオパーソナリティ)